もくじ
- 【報告1】公開保育
- 【報告1】秋田喜代美先生 荒尾第一幼稚園の公開保育を参観後の講評 要約
- 【報告1】園内環境見学11:30-12:00
- 【報告2】「子どもたちの声と見方・考え方」を伝えるポスター掲示
- 【報告2】「科学する心」を探す事例 ポスター討議
- 【報告3】保育と小学校の連携パネルディスカッション
- 【報告3】論文の実践 論文のその後実践 発表
- 【報告3】秋田喜代美先生と荒尾第一幼稚園職員との対談
- 【報告3】秋田喜代美先生講演「科学する心でつながるまなざし」要約
- 【報告3】質疑応答・感想
- 【報告4】アンケートでいただいた質問への回答
- 【報告4】実践発表会アンケートレポート(まとめ)
- 【報告4】実践発表会アンケート
- 【報告4】謝辞とspecial thanks
保育と小学校の連携パネルディスカッション 14:10-14:40

保育と小学校の連携パネルディスカッション
後半のプログラム「保育と小学校教育の連携」をテーマにしたパネルディスカッションを実施しました。ファシリテーターは秋田喜代美先生(学習院大学教授・東京大学名誉教授)、パネリストには荒尾市立清里小学校 校長の塩村先生、荒尾第一幼稚園 園長の宇梶達也、年長担任の増永彩希、本園職員であり小学生の保護者でもある池田真由子が登壇し、多角的な視点から意見が交わされました。
冒頭、秋田先生からは、荒尾第一幼稚園と清里小学校との日頃の連携の取り組み【便りの交換や、塩村校長による園だよりへの丁寧なフィードバック】が、全国的にも稀な実践例として紹介されました。
塩村校長は、幼稚園での子どもの姿から学ぶ姿勢に感銘を受けたと述べ、「学び合いとしての連携」への期待を語られました。特に、園職員によるドキュメンテーションに込められた子ども理解の深さや、環境構成の意図に触れ、小学校側が学ぶ姿勢を持つことの重要性を共有されました。
宇梶園長は、幼稚園側が小学校の教育内容を知ろうとする必要性を語りました。その一例として、小学校教員と近隣の幼稚園・保育園職員との話し合いの場を設けたこと、小学校の学力テストを職員で実施してみた経験などを紹介し、「テストは単なる知識の確認ではなく、思考力や理解力を問うものである」ことを実感したと語りました。
増永教諭(年長担任)は、小学校の算数の学力テストに挑戦した際の気づきとして、「公式に当てはめて解くのではなく、問いを正確に読み取り、情報を整理して答える力が求められている」と話し、現在の本園で行なっている幼児教育とつながっていることを感じたと述べました。

池田職員は、自身の子どもが小学校に進学した際に感じた違和感、【「幼児期は失敗を肯定的に受け止められていたのに対し、小学校では正解/不正解が重視され、挑戦することが難しくなる」という感覚のギャップ】を、保護者としての視点から共有しました。
この発言を受けて、塩村校長は「失敗を面白いと感じる心を育てることが大切」と述べ、体育指導の事例を交えながら「できる・できないを行き来できる安心感」を保障することの意義を語られました。また、「子どもが『やってみたい』『面白そう』と思える仕掛けづくり」が求められるとし、小学校の柔軟な教育環境の必要性を指摘されました。
宇梶園長は、本ディスカッションに向けて近隣の保育園・認定こども園・小学校校長との対話の場を2回設けたことを紹介し、「継続することが連携の深化につながる」と話しました。また、ソニー教育財団「つながるまなざし研究会」のリーフレットに掲載された“おしながき”が、保育者と小学校教員の対話の糸口として有効であることにも言及しました。
さらに今後の取り組みとして、「卒園児から寄付されたランドセルや教科書を年長児の環境構成に活用すること(亀山先生が紹介)」や「図書館探検などの体験的な接続活動(秋田先生が紹介)」を実施したいことも共有されました。
塩村校長からは、小学校での要録の活用について報告がありました。幼稚園から提出された要録は学校全体で共有され、入学初期の子どもの状況把握と適切な支援に役立てられているとのことです。
また、増永教諭と池田職員からは、「園と小学校の先生が互いの教育現場をより深く理解し合うためには、業務連絡に留まらず、理解し合う対話の機会が必要である」との提言がなされました。
秋田先生から、小学校の校長先生に「なぜ幼保小連携がうまくいかないのか」を校長先生に聞き取りをする研究をしているが、その中の話で「園の先生が小学校1年生の教科書を見たことがないという人が結構いる」「相互参観や授業見学ももちろん重要だが、園側が小学校の学びに関心を持ってもらうとまた違う」という話があったことが語られました。秋田先生が実際に会場で「小1の教科書を全部見たことがある園の先生はどれくらいいますか?」と尋ねた際、挙手する人はごくわずかでした。
地域の取り組みの一例として、図書館活用についても触れ、「1年生になる前に図書館の使い方を知っているだけで、学校生活の入り口がずいぶん違ってくる。図書館探検などを通して、園児が学校の空気に触れておくことも大切」と提言されました。
最後に秋田先生は、「教育長が幼保小接続や授業改善を“一体のもの”として熱意を持って推進している自治体は、例外なく成功している」とお話されました。そして、教育長が過去にソニー教育財団の実践論文を執筆された経験を持つ方であることにも触れ、「まさに深いご縁がある方。この機会にぜひお話を聞かせていただきたい」と語られました。
教育長から、自身がかつてソニー教育財団の実践論文を執筆した経験にも触れられました。全国の教育長の大会でも架け橋の話があり、キーワードとしては「さらなる連携」。今までも連携をしているけれど、今日のお話で、もっと幼稚園保育園と小学校の連携をやらなければいけないというとコメントがありました。
最後に秋田先生から「ぜひこれから荒尾市のますます、保幼小連携接続、まなざしの共有をお進めいただけたらと思う」と総括されました。
論文の実践 論文のその後実践 発表 14:50-15:05

2024年度 年中組「科学する心を育てる保育」実践レポート
年中組担任 藤原
本園が考える「科学する心」とは、「自分の思いを実現しようとする力」「友達と協力して課題を解決しようとする態度」、そして「環境と対話しながら心を働かせる感性」です。今回は年中組で取り組んだ「ロボットの出てくる映画づくり」を通して、園生活に埋め込まれた“創作意欲”の姿をご報告します。
【きっかけは「見てほしい」という思い】
この実践は、子どもたちのショーごっこから始まりました。「たくさんの人に見てほしい」という気持ちが高まり、遊びの延長として映画づくりへと発展。絵本を参考にしたり、園内にある素材を工夫してロボットを作る子どもたちの姿がありました。
【試行錯誤の中で育つ「科学する心」】
中でも印象的だったのが、Aちゃんの取り組みです。自作のロボット「ロビン1号」を動かしたいと願ったAちゃんは、工房にある戸車を思い出し、キャスターで動かす方法を考えました。ガムテープで固定するもうまくいかず、キャスターの取り付けにも苦労しながら、最終的には片足に3つずつ、計12個のキャスターを取り付けて安定した動きに成功。何度も試し、失敗を重ねながら工夫する姿には、「環境と対話する感性」や「課題解決への粘り強さ」が表れていました。
【 解体とリサイクル──ものとの対話の深化】
映画の撮影後、子どもたちの間で「ロビン1号はこのあとどうするの?」という問いが生まれました。話し合いの末、未完成のものは年長組へ、完成品は解体して素材として残すことに。しかし、「壊したくない」というためらいの声もありました。 そのとき、園長が「リサイクルって知ってる?」と問いかけたことをきっかけに、子どもたちは素材が新しく生まれ変わることに気づきます。多様な素材がいつもある環境が、自然にリサイクルの概念を受け入れる土壌となっていたと感じました。
【翌年へ引き継がれた“記憶と創作意欲”】
この映画づくりの様子を見ていた翌年度の子どもたちは、年中になってすぐ「自分たちも映画を作りたい!」と声をあげました。半年かけて恐竜の映画を制作し、撮影後の解体では「これはリサイクルするんだよね」と理解を示す姿がありました。 段ボールとガムテープを分別したり、「ガムテープばっかり捨ててる。別のもので貼ればよかったね」と振り返る姿も。また、恐竜のヒレだった部品をロッカーに保管し、新たな作品をつくった子が、「見て!リサイクルできた!」と嬉しそうに報告してくれました。
【保育者の関わりと環境の力】
子どもたちが記憶や経験をもとに新たな創作に向かい、仲間と協力しながら課題を乗り越えていく中で、保育者の役割は“環境の再構成”にあります。素材の配置、活動の場のつくり方、声かけのひとつひとつが、創作意欲を支える仕掛けとなります。
【おわりに──「科学する心」を確かに育むために】
この一連の実践を通して、私たちは「園生活に埋め込まれた創作意欲」の大切さを再認識しました。子どもたちは、自分の思いや過去の経験をもとに新たな意欲を生み出し、環境や仲間との対話を通じて「科学する心」を育んでいます。
2024年度 年長組「科学する心を育てる保育」実践レポート

年長組担任 増永
私たちは、「科学する心を育てる」保育の手立てとして、次の3点を大切にしています。
1.園生活に埋め込まれた記憶や経験が、遊びの出発点となること
2.以前の活動が影響し、新たな創作や発見へつながっていくこと
3.活動を振り返り、もう一度見つめ直す機会(「もう一度」の時間)を保障すること
これらを踏まえ、2024年度の年長組が取り組んだ「お化け屋敷」の実践をご紹介します。
【記憶がつなぐ創作意欲】
この活動の出発点は、前年の年長組のお化け屋敷に招待された楽しい思い出でした。「自分たちもやってみたい!」という願いが、今年のお化け屋敷へとつながりました。 製作の中では、過去の成功体験が生かされる場面もありました。たとえば、ろくろ首の体を作る際には、ダンボールに白い紙を貼ってから色を塗る方法が用いられました。これは以前の製作で「うまくいった」という記憶から応用されたもので、他のおばけにも展開されました。
【「もう一度」の機会が生んだ工夫と達成感】
完成後、子どもたちは役割を決めて練習し、本番では年中・年少の子を招きました。しかし、暗い部屋に驚かず静かに出ていく様子を見て、「驚いてない?」と気づきます。そこで振り返りの時間をもち、「どうしたらもっと驚いてくれるか?」と話し合い、動きのある演出を追加。結果、初回よりもドキドキ感が増し、達成感に満ちた表情を見せていました。
【光から宇宙へ──発想の広がりと探究心】
お化け屋敷のあとの活動では、OHPやCDを使って光で遊ぶコーナーが登場。「夜みたい」「宇宙みたい」といった声が上がり、宇宙をテーマにした立体製作へ発展。図鑑を見ながら色を調合し、「本物みたいにしたい」と試行錯誤を重ねました。失敗を経て、素材を吟味し、納得のいく形を追求する姿が見られました。
【振り返りから生まれる「科学する心」】
年長組になると、問題に直面したときに手を止めて考えたり、友達と話し合ったりする時間が自然と生まれます。友達の言葉からヒントを得たり、以前の活動と結びつけて発展させたりと、主体的に問題解決に向かう姿が育っていきます。
「振り返りの時間」が子どもたちの学びを深め、確かな「科学する心」を育む鍵であると考えています。
秋田喜代美先生と荒尾第一幼稚園職員との対談(要約)

登壇者:•秋田喜代美先生(学習院大学教授)
•コーディネーター:中ノ子先生(尚絅大学短期大学部)
荒尾第一幼稚園 職員
•( 園長)宇梶達也 •増永彩希(年長担任 論文執筆時)
•藤原汀紗(年中担任 論文執筆時)•松川夏海(年少担任 論文執筆時)
登壇者:•秋田喜代美先生(学習院大学教授)
•コーディネーター:中ノ子先生(尚絅大学短期大学部)
荒尾第一幼稚園 職員
•( 園長)宇梶達也 •増永彩希(年長担任 論文執筆時)
•藤原汀紗(年中担任 論文執筆時)•松川夏海(年少担任 論文執筆時)
秋田先生は冒頭で配された事例集を見て「荒尾第一幼稚園の振り返りには“ぐっとくる”力がある」と評価され、子どもたちの経験を「面白かったね」で終わらせず、内面や気づきを丁寧に掘り下げる文化に注目し、「この必要性を全国の先生に伝えてほしい」と語られました。
中ノ子先生から本園の「科学する心」に込めた思い、という問いに、宇梶園長は「幼稚園教育要領解説」の冒頭に記されている“2030年を生きる子どもたちに求められる力”に言及しながら語った。「これからの子どもたちは、過去の正解では解決できない未来を生きていきます。そのためには、自ら課題を解決していく力が必要です。その力は、製作やプロジェクト活動の中で、友達と協力しながら育まれると考えています。数日間続くプロジェクト活動に限らず、3歳児が園庭で漏瑚や雨樋を使い水はどう流れるのか、と試す様子を挙げ、素材との出会いや友達とのやりとりを通じて、試行錯誤しながら学びを深めています。このような日常の中でも『科学する心』育まれると思います」
年長組担任増永は「提案はしない、確認はする」を実践していると述べた。「今、何に困っている?」と問いかけることで、子どもたち自身が考え、失敗を繰り返しながら自ら道を探っていくという。
年中組担任藤原は、光と色の遊びを通じて、子どもたちが道具の使い方を自ら試行錯誤する様子を紹介。気づきを待つことの大切さを実感したと語る。
年少組担任松川も「子どもから出たアイディアはまずやってみる」「材料をたくさん用意する」ことが、自発的な創造につながると話した。
宇梶園長は、保育のふり返りとして「写真を用いた園内研修」を紹介。週に1回、子どもの気づきや工夫の瞬間を共有し、職員間で語り合うことが、保育の質を高める土壌になっているという。全職員が簡単なドキュメンテーションを作成し、相互に気づきを深めている。
ロボット製作の事例では、子どもたちが“別れ”を意識しながらリサイクルを行なったことが紹介された。保護者から「素材と別れ、また再生させる経験は、人生の深みにもつながる」と書かれた手紙をもらったことが紹介された。
宇梶園長は、ICTの活用も紹介した。「映画の音探し」や「iPadでのアフレコ」など、創作活動に組み込むことで、子どもたちの表現が広がっていると述べた。保護者にもICTの意図を伝えながら進めており、“創作活動の道具”として使っているという。
保育実践の論文化について、藤原・増永・松川の各先生が「写真や記録を振り返る中で、子どもの変化に気づくことができた」と口を揃えた。文章化は大変そうに見えて、実際には日々の積み重ねが活かされる作業であり、保育者自身の“見る力”を育てるプロセスになっているという。
最後に中ノ子先生:
「今日の対談を通して、子どもたちがものを作ったり、挑戦する姿を大人が心から応援していること、そして大人自身も一緒に試行錯誤を楽しんでいることがよく伝わってきました。
午前中見学された他園の先生方からも「自園でこうしてみたい」という声が上がっていました。実践発表会が日本のいろいろなところで子どもたちの幸せのために花開いてくることを期待しまして対談を終わりとします」と語った。
秋田喜代美先生講演「科学する心でつながるまなざし」要約 15:30-16:05

(実際の講演を荒尾第一幼稚園が要約しています)
秋田喜代美先生(学習院大学教授・東京大学名誉教授)は、ソニー幼児教育支援プログラムの設立時から携われていた。
ソニー教育財団と「科学する心」
井深大氏の理念に基づき、2000年に財団が設立。「科学する心」は「理科」にとどまらず、「探究」「創造力」「未来志向」を重視。日本の優れた幼児教育実践を広めることを目的に、全国の園が実践を公開・共有している。
「探究的な学び」は今後の教育全体の柱になる。幼児教育から小・中・高へつながる探究の連続性が重視され、情報活用力・言語力とともに育まれる必要がある。
荒尾第一幼稚園の保育の特徴は「環境との対話」を軸に、園生活に創造的活動が埋め込まれている。
•子ども一人の思いやこだわりから始まり、それが友達や社会とのつながりへと発展。
•探究のプロセスには「意欲・見通し・振り返り」が欠かせず、保育者が感性で支える実践が見られる。
活動が広がっていき、繋がる様子を丁寧に捉えている。
まずは一人の活動の中で好きなこと、こだわりを大事にしている。それがさらに仲間とつながっていく。さらに本物の社会や世界に繋がっていく。今日の実践の中で「自分はこれがしたい」、友達との関わりで「これもやってみたい」という事例がたくさんあった。
深まる時に大事なのは意欲や見通し振り返り。上手くいかないことに、「ショーを見てくれるお客さんがいないのは、どうしてだろう」「誰も、お化け屋敷なのに驚いてくれない。どうしよう」というような、立ち止まりが起こる。そこを保育者がすぅっとすくって、もう一度向かっていく日々が探求のポイントである。パターン化しないで保育者の感性で行われている、問い返しが良いと思う。
リサイクルということで言うと、みえているものだけじゃなくて知らない世界にもう一度気づきを与える。宇梶先生が「リサイクルって知ってる?」と伝えることによって、段ボールなら段ボールをもう一度見直して、部品とか何に使えるんだろうと思うのが大きな特徴になっている。
井深氏の「ものをつくる苦労を知る人は人のせいにしない」という言葉を引用し、心と意識をもったものづくりの重要性を説く。荒尾第一幼稚園では「工房」が環境にあり、子どもたちが創作活動とつながる経験をしている。
探究コミュニティは1人1人のわくわくが、今日皆さん参加されて荒尾第一幼稚園の保育実践や発表にみんなのわくわくになったと思う。23年間の「科学する心」の歴史的な知見とそれと共にまた新たな実践を作りだしていくのが大事と語られた。
質疑応答・感想(16:05~16:20)
・一番最初に西南学院大学の門田理世先生より感想をいただきました。
「午前中の保育を見せていただきましたが、少子化で先生も少なく大変な中、本当に大きな保育だと感じました。先生方の子ども達への思いと保育環境への思いが伝わってきました。小さな世界の中にある大きな保育を見せていただきました。」
(※掲載確認のメールのお返事に「大きな保育の意義について」書いてくださったので、合わせて掲載いたします)
「大きな保育の意義」について
この遊びの先にある未来へと生きる子ども達の持つビジョン
この遊びを通して子ども達と共に新たな世界の扉を開けようとする保育者のビジョン
この遊びの中に生きる子ども達や保育者を外の世界とつなげて更なる可能性へと導こうとする園のビジョン
いずれもとてつもなく大きく、そして、広い世界へとつながりたいと思う『心』の声が聞こえる保育でした。
・続いて参加者から、毎週行っている写真を使った研修について質問があり、宇梶園長からは「写真を通してイメージを共有しやすくなる」と説明がありました。秋田先生からは「振り返りの時間を取ることが深まりにつながる」という補足もあり、研修の質を高める工夫が共有されました。
・廃材や素材の集め方については、保護者協力のほか、前園長が大切に集めてきた素材を活用していると紹介がありました。
・週案・月案の書き方に関する質問では、「ねらいを立て、環境構成や関わり方を考え、子どもの姿を振り返りながら記録を更新する」との実践的な説明がありました。
・「卒園生は、小学校中学校でどのような活躍や姿が、何かお話があったら聞かせてほしい」と質問がありました。宇梶園長が教育長にお願いすると、
教育長より「高校生たちが、市立図書館の施設を利用して自主的に小学生に、夏休みや冬休み勉強を教えようと活動をはじめた。まわりが投げかけたものでなく自主的なもの。一人一人が通う高校は違うが、元は荒尾第一幼稚園の同級生というつながり。後輩たちが今もなお行っている。」との紹介がありました。
閉会
参加いただいた皆さん、ありがとうございました。
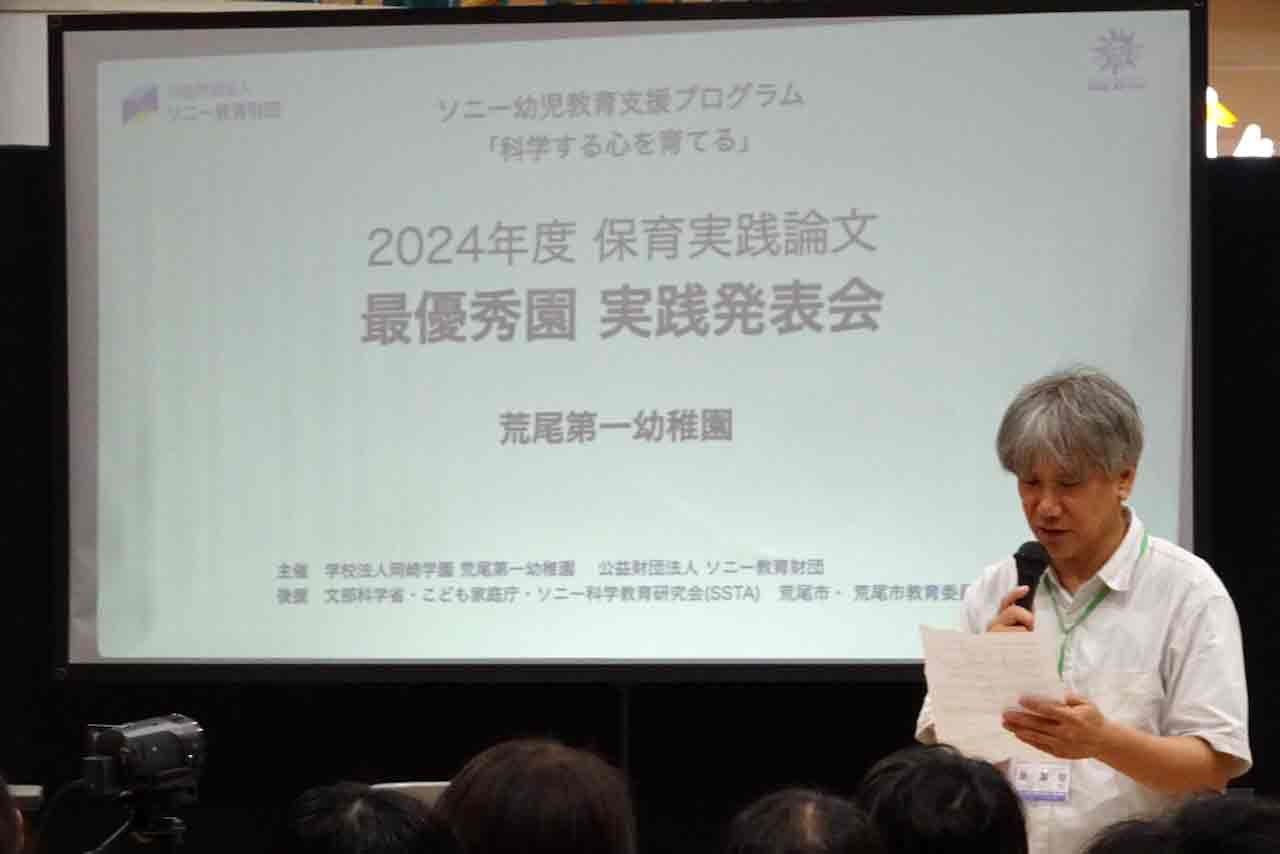
もくじ
- 【報告1】公開保育
- 【報告1】秋田喜代美先生 荒尾第一幼稚園の公開保育を参観後の講評 要約
- 【報告1】園内環境見学11:30-12:00
- 【報告2】「子どもたちの声と見方・考え方」を伝えるポスター掲示
- 【報告2】「科学する心」を探す事例 ポスター討議
- 【報告3】保育と小学校の連携パネルディスカッション
- 【報告3】論文の実践 論文のその後実践 発表
- 【報告3】秋田喜代美先生と荒尾第一幼稚園職員との対談
- 【報告3】秋田喜代美先生講演「科学する心でつながるまなざし」要約
- 【報告3】質疑応答・感想
- 【報告4】アンケートでいただいた質問への回答
- 【報告4】実践発表会アンケートレポート(まとめ)
- 【報告4】実践発表会アンケート
- 【報告4】謝辞とspecial thanks