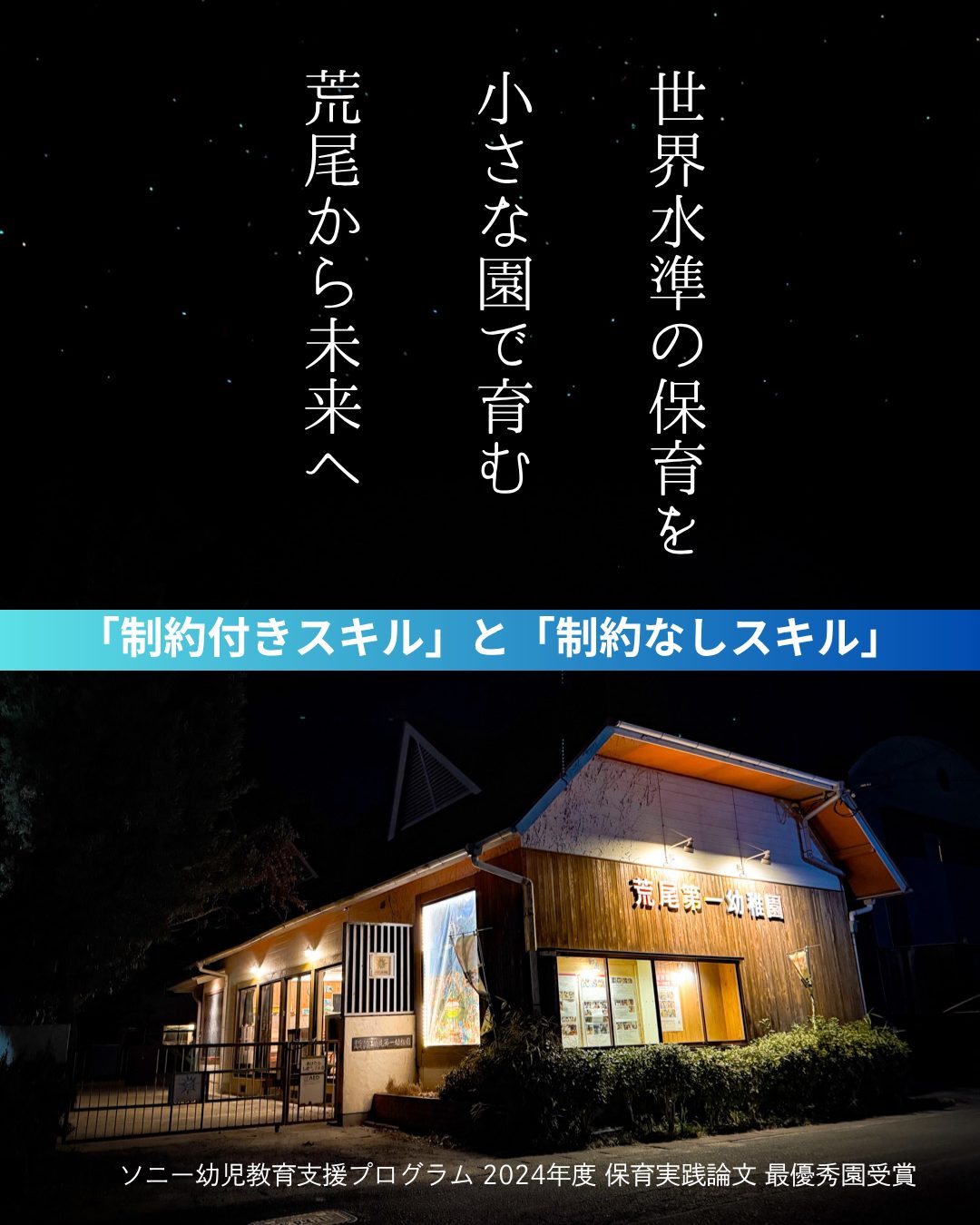幼稚園でしか育たない学び
ソニー幼児教育支援プログラム 最優秀園 受賞
小さな私立幼稚園が受賞できたのは、ここにある遊びが、 これからのを生き抜くために不可欠な 『科学的探究心』だと、 認められたからだと思います。
年中組のボンド×段ボール製作。
最初は、テープで作り慣れていた子どもたちの前に、そっと木工用ボンドを置くだけでした。
すぐには使われません。いつもの方法で作る方が安心だからです。
そこで保育者は考え、ボンドと子どもたちを結びつける環境を考えて構成しました。
(ここが保育の大切なポイント)
すると興味が動き出し、筆でボンドを塗りながら静かに集中して作り始める子どもたちの姿がありました。
⸻
■ 技法を覚える“制約ありスキル”からはじまる学び
最初の段階では、
「くっつける」「立たせる」などの「技法の習得」が中心。
これは 制約ありスキル と呼ばれる、手順が明確で繰り返しで身につく力。
ここまでは家庭でもできる学びです。
しかし幼稚園では、
環境・仲間・継続性があることで、
「制約ありスキル」と「制約なしスキル」が自然と結びつき、学びが大きくふくらんでいきます。⸻
活動が続くうちに、倒れる・崩れる・立たない…という“問題”が次々出てきます。
すると子どもたちは自分で考え始めます。
• 支えをつける
• 角を作って安定させる
• 重いものは下にする
• 窓を作るにはどうしたらいい?
• 光を入れるにはどこを開ける?
こうして、技法を“目的に合わせて作り変える力”が育ちます。
これは 制約なしスキル と呼ばれる、幼児期から一生育ち続ける力。
⸻
■ 経験がつながり、構造の理解へ
家、公園、テーブル、複雑な建物…。
作品は次第に立体的・構造的になり、
“構造がわかると、表現が広がる”という経験が生まれました。
コマづくりで覚えた「折って穴をあける技法」を思い出し、
段ボールの窓づくりに応用した子もいました。
⸻
■ さらに深い学びへ:ショベルカーとリサイクル
9月には、子どもが乗れる大きなショベルカーに挑戦。
アームが壊れ、何度も試している中で、
「ここにボンド塗ったらいいかも!」という“ひらめき”が生まれました。
10月には消防車を解体し、
「壊す」と「リサイクルする」の違いに気づき、
材料として再び息を吹き返す段ボールにワクワクし、
複雑な感情や循環の価値に触れていきます。
これは家庭ではなかなか育ちにくい、幼稚園だからこそ生まれる学びです。
こうした 経験の連続性(環境に埋め込まれた記憶) が働くのも荒尾第一幼稚園の学びの特徴です。
⸻
■ 最後は“共同創造”へ発展する
ハロウィンパーティーが近づくと、
作る・動かす・飾る・演出する・話し合う……
この数ヶ月で育った力が表現へ結びついていきました。
影をつける演出、滑車で動くお化け、ライトの灯る家。
ひとりの製作が、共同製作へとつながる瞬間。
⸻

■ この学びは「幼稚園でしか育たない」
ボンドので作った作品は
立体へ、構造へ、空間演出へ。
友だちの姿に刺激を受け、
試行錯誤を重ね、
一度離れ、また戻って挑戦するプロセス。
壊れる・できない・くやしい・できた・うれしい。
そんな複合感情と一緒に、
子どもたちの学びは深まっていきました。
これは教科書にもアプリにもない、
幼稚園という環境でしか育てられない学びです。